三者間相殺契約
執筆者
- 三者間相殺契約とは三者間相殺契約(三者相殺)とは、例えば、以下のような事例において、甲乙丙間で、B債権が差押えられた等の場合に、A債権とB債権とを『相殺』することを予め合意しておき、実際に差押え等がなされたときに、当然に、または、『相殺』の意思表示により、A債権とB債権とを対当額にて『相殺』するという契約(合意)のことです。
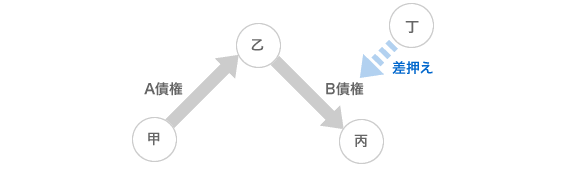 例えば、甲が原材料を乙に売却し、乙がその原材料を製品に加工し、乙がその製品を丙に売却する場合であって、甲丙がグループ企業である等甲丙間が密接な関係を有しているときに、乙の破綻によりA債権の回収ができない可能性を考慮し、甲丙の要請により三者間相殺契約が締結される場合があげられます。また、乙に比して甲丙の信用力が低い場合に、乙の希望により三者間相殺契約がなされる場合も考えられます。三者間相殺契約は、例えばA債権を保全したい甲の立場から見ると、抵当権等の手続的に重たく、当事者の抵抗が予想される担保権を利用するのではなく、関係する三者間の契約にてA債権の保全ができることとなり、相当簡便である等の理由から、実務的には利用されることが多いようです。
例えば、甲が原材料を乙に売却し、乙がその原材料を製品に加工し、乙がその製品を丙に売却する場合であって、甲丙がグループ企業である等甲丙間が密接な関係を有しているときに、乙の破綻によりA債権の回収ができない可能性を考慮し、甲丙の要請により三者間相殺契約が締結される場合があげられます。また、乙に比して甲丙の信用力が低い場合に、乙の希望により三者間相殺契約がなされる場合も考えられます。三者間相殺契約は、例えばA債権を保全したい甲の立場から見ると、抵当権等の手続的に重たく、当事者の抵抗が予想される担保権を利用するのではなく、関係する三者間の契約にてA債権の保全ができることとなり、相当簡便である等の理由から、実務的には利用されることが多いようです。
しかし、民法が規定する相殺(民法505条以下)は、例えば、甲が乙に対しA債権を有しており、乙が甲に対しB債権を有している場合に、甲または乙が相手方に対して相殺の意思表示をすることにより、A債権とB債権とが対当額にて消滅するものであり、対立する債権を有する二当事者間での相殺であって、民法の相殺(民法505条以下)の規定は、当事者を3名とする上記のような『相殺』の場合を想定しておりません。
そこで、このような『相殺』の契約(合意)は、対内的に有効か、また、対内的に有効であるとしても、対外的にも有効か、が問題となります。
- 対内的効力上記1記載のとおり、三者間相殺契約については、民法が想定していない契約類型となりますので、まず、対内的にそのような契約が有効であるのか、すなわち、差押債権者である丁その他の外部の第三者を除外して、甲乙丙の間でだけ考えたときに、三者間相殺契約がその三者間の内部において有効であるのかが一応問題となりますが、契約自由の原則等からして、対内的には有効であるとされております(大判大正6・5・19民録23輯885頁)。
- 対外的効力対内的効力は上記2のとおりとしても、三者間相殺契約の対外的効力、すなわち、甲乙丙間にて三者間相殺契約を締結していた場合であって、上記1の図のように丁がB債権を差し押さえてきたときに、甲乙丙は、丁に対して、B債権の消滅等を主張できるのか、という問題があります。かかる三者間相殺契約の対外的効力については、最判平成7・7・18(判時1570号60頁)(ただし、当該判例は、二当事者間の相殺契約であり、上記1の図で言えば、甲乙間の相殺合意がなされていた事案についての判断となっております。)が現れて以降、積極的に議論がなされ、種々の見解が提示されているところであり、その見解のまとめ方にも種々の方法があるかと存じますが、当職なりにまとめますと、以下のとおりになるかと存じます(ただし、各種契約そのものについて、破産法等に定められた否認権行使の可能性は、別の問題として、考慮が必要です。)。(1) 既存の制度を利用して説明する説
三者間相殺契約の『相殺』を、民法典にはないがそのような『相殺』であると正面からとらえることはせず、債権譲渡(担保)、債権質、(免責的)債務引受、第三者弁済等、既存の制度を利用して説明(構成)する考え方があります。
たとえば、上記1の図でいえば、甲乙丙の三者間相殺契約は、
・甲が、A債権を被担保債権として、乙から、B債権を債権譲渡担保により取得した、
・甲が丙に対しA債権を譲渡した、
・甲がB債権にかかる債務を(免責的)債務引受により丙から引き受けた、
・甲がB債権を第三者弁済(相殺)した、
等と構成されます。
この考え方によれば、異なる考え方をするものもありますが、三者間相殺契約が対外的効力を有するか否かは、既存の各制度の対外的効力の問題として整理されることとなり、各制度の対外的効力を個別に検討することとなります。
(2) 三者間相殺契約そのものを正面から認める説
三者間相殺契約の『相殺』を、民法典にはないがそのような『相殺』であると正面からとらえ、既存の制度を利用せずに、その『相殺』自体の効力として対外的効力が認められるか否かを検討する考え方があります。
この考え方において、どのような場合に対外的効力が認められるか否かについて争いがあり、
i ) 三者間相殺契約について確定日付が取得されており、かつ、差押え等第三者が介入してくるまでの間に、当該三者間相殺契約の効力が生じていなければならないとする説、
ii ) 三者間相殺契約について確定日付が取得されている必要があるが、差押え等第三者が介入してから当該三者間相殺契約の効力が生じても、当該第三者に対抗できるとする説、
iii) 三者間相殺契約について確定日付も不要であり、かつ、差押え等第三者が介入してから当該三者間相殺契約の効力が生じても、当該第三者に対抗できるとする説
との考え方に整理できるのではないかと考えます。
この点、現時点では議論が錯綜しており、どの考え方が妥当かは、今後の判例の集積を待つほかないのですが、甲乙丙に実務上の障害がないのであれば、上記 (1)の考え方を前提に、既存の制度の組み合わせにより、三者間相殺契約を構成するべきであると考えます。
他方、甲乙丙のうちの一部当事者の反対等により、上記 (1)のような構成を採ることが出来ない場合で、上記(2)の考え方を前提に三者間相殺契約を締結しなければならないときであっても、最低限、当該契約には確定日付を取得しておくべきであると考えます。
- 実際の活用方法理論的な分析はともかく、実際に三者間相殺契約が利用されている場合における契約内容は、各種文献および当職の経験からして、上記3の(1)や、上記3の(2)のi、iiが多いように思われます。顧問先の皆様のご経験上、取引先の要請に応えて、上記1の図のような取引をしておられることもあろうかと存じます。その場合、例えば乙が破産した場合であって、三者間相殺契約のような保全措置を講じていなければ、B債権を破産管財人から全額請求されたうえで、A債権は破産債権となり、配当にあずかるしかなくなります。現在の顧問先の皆様の取引における債権債務関係を確認し、上記1のような状況にあるのであれば、三者間相殺契約の締結等を検討されるべきであると考えます。
- 追記なお、三者間相殺契約といっても、上記1の場面以外にも、丙が甲に対してC債権を有しており、3つの債権(またはそれ以上の数の債権)が存在する場合、三者ではなく四者、五者となる場合や、丙の協力が得られず、三者間契約とならずに甲乙の二者のみで合意する場合など、具体的な事例に則して種々のパターンが考えられるところです。また、近時の停止条件型の債権譲渡担保における最高裁判例(最二小判平16・7・16民集58巻5号1744頁、最三小判平16・9・14判タ1167号102頁)を踏まえ、上記3の(1)の構成を採るとしても、契約の効力が契約締結時に確定的に生じるような内容とする必要がありますし、また、上記3の(2)の構成を採る場合であっても、前記2つの最高裁判例の考え方を踏まえてその内容を規定する必要があろうかと存じます。いずれにしましても、一度、顧問先の皆様の取引における債権債務関係を分析していただき、もし、三者間相殺契約締結の必要性等を感じられましたら、事前に当事務所までご相談いただきますようお願いいたします。

